こんにちは!橋本恵子です。珍しく疲れが出て、早朝レッスンの後、数時間、ダウンしていました。明日からの新年度本格スタートに向けて、身体がリセットを要求したのかもしれません。お昼過ぎにムクムクと起き出して、アイドリングを兼ねて(笑)ブログに向きあっています。
さて、私。今年初めから、「書く」ということと、自分なりに向きあっています。日常的に、FACEBOOKは「日々のひとりごと」を、HPの当ブログは「ひとりごとの中から、少し掘り下げてみたいと思ったこと」を、さらにnoteには「ビジネスに役立ちそうなこと」を、と、自分なりに区分けしながら、書いています。私のキャリアのスタートはアナウンサーで、原稿を「書く」ということから始まったわけですが、あれから30年以上、「書く」ことを続けてきて、今さらながら、なぜ、私は「書く」ことをやめられないのだろうか?「書く」ことを通して、何がしたいのか?と、考えてみたくなったのです。
中学生のころから「アナウンサー」を夢見ていましたが、それと並列で「新聞記者」にも憧れていました。当時、いや、小学生のころから、読書感想文とか、作文など、およそ子どもたちが嫌がる「書く」ということを、イヤだと思ったことはありませんでした。題材によっては、時間がかかることはありましたけれど。
だからといって、ものすごく「本好き」だったということはなく、普通よりちょっと好きかな?というくらいでした。本を最も読んだのは、思いがけない転勤で、通勤時間が往復2時間になってしまった東京支社時代。座席が確保できない往路は文庫本(軽めの小説)、ライナーで夕飯を食べながらの帰路は、ビジネス系(本は思いが軽めのビジネス書)を読んでいました。速読などは学んでいませんが、読むスピードは速いので、1日1冊ペースでした。
ということで、少し話がそれましたが、子どもの頃は、そこまで本好きでもなく、書くことを学んだわけでもないのに、なぜ書くことが好きになったのかなぁ…と、考えてみると、ひとりでいることが多かったからかな?と。富士山のふもとの農家に育ち、3姉弟の真ん中で、子どもの頃、私だけがやや病弱(小児喘息もち)でした。週に1回は、町の病院にかかっていて(母が受付して、受診までは置き去り)、ひとりの時間の過ごし方として「想像すること」が好きだったこともあるかと思います。それを、自分の存在とともに、「書く」ことで表現したかったのかもしれません。
「認めてほしかったのか?」と問うと、そういう気持ちも少しはあったんだろうと思いますが、賞を頂けるのは嬉しかったけれど、むしろ、書いた文章に、先生がどんなコメントをしてくださるかが、楽しみでした。その証と言うわけでもないのですが、頂いた賞状は、どこかに行ってしまったけれど、今でも、中学時代・高校時代の作文を何点か手元に保管していて、時々、取り出しては、先生からのコメントと共に読んでみることがあります。拙い文章ですが、熱が高く!作文でも感想文でも「自分」を持ち出していることが特長で、内容は「反省」がメーン(笑)。起きた出来事(読書感想文場合はその内容)に、自分が感じたことを言わずにおられず、圧倒されたり、共感したり、驚いたり、泣いたりしながら、そこから自分が気づいたことを、ただただ、表現したくて書かずにおられなかったのだろうなぁ、と思います。
自分探求が、昔から、好きだったんですね。
目に見える世界は、全部、自分を通してしか見えていないから、言語化することで確かめたいのかもしれません。確かめたいのは、誰かの共感や「いいね」ではなく、書いているうちに「ああ、私は、こんなことを考えていたんだ」とか「こんな風に考えるようになったのは、きっと、あんなことがあったからだ」と、掘り下げて、紐づけていく、繋げていくことが好きなんです。
と・・・今日もブログを書きながら、私が「書く」ことをやめられない理由が、垣間見えた気がして、ちょっと嬉しく思います。
これが、きっと、私の「書く」ことの根っこにあることです。だから私は「書く」んだと思います。
ところが、いや、幸いにして…なのか(好きが高じた結果ともいえるけれど)、私はアナウンサー・記者という仕事をに就くことで「書く」「話す」ということを求められるようになり、不特定多数の方に「伝える」ことと向きあうことになりました。そこではこれまでの「ひとりよがり」では太刀打ちできなくなったのです。それが仕事で、お給料をもらっているのに「伝わらない」ことに直面して、どうしたら「伝わるのか」を、考えるようになりました。※ここからの「書く」との葛藤は、また、機会を見つけて…
週末、こちらの本を読みました。直感で購入したので、失礼ながらpatoさんのことは、本を読むまで存じ上げなかったのですが、chatGPTなど、書くことにもAIが台頭してくる中で、やっぱり自身の「気持ち・感情」をが中心にあることを忘れてはいけないなと、思いました。

客観性は大事だけれど、それでは人の心は震えない。それらの基礎を押さえつつ、ある一瞬だけその客観性から飛び出す必要がある。
認められなくとも報われなくとも、ただ自分が信じるものを積み重ねていく。
ただ、読んで終わり!ではなく、こうして本を読んで、私自身が感じたことを「書く」ことで、自分にインプットできることも「書く」ことの醍醐味だとも思います。感じることは、みんな違いますしね。
だから、私は、今日も「書く」ことを、やめられないんですね。これからも、書き続けます!






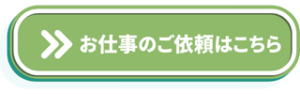









この記事へのコメントはありません。