9月24日開催の、地元・常葉大学コミュニケーション講座。有志の学生さんたちが集う「アンテナ高めの」学び場です。今年も申し込みと同時に、いくつかの質問を頂戴していますので応えていきましょう。(これが私の最大の学びです、感謝)
Q2:抑揚のつけ方のコツを教えて
今回の講座はテーマが「発表篇」。大学生もプレゼンの機会もあるでしょうし、就活やアルバイト先での面談などで、話す力を試されることも多いでしょう。講座では実際に話していただいた上で、個別アドバイスも予定していますが、頭で「わかる」ことも大切なので、思いつくままに書いてみますね。
小学館 デジタル大辞泉によると「抑揚」とは
話すときの音声や文章などで、調子を上げたり下げたりすること。イントネーション。を言います。
質問者さんが、その「コツ」を知りたいということは、一本調子の平坦な「話し方」では、伝わりづらいと思ってらっしゃるからですかね。目の付け所がGOODです、というのも、「伝わる」と「伝わらない」を分けるのは「イントネーション」にあると言っても過言ではないからです。
伝わる「話し方」で大切なのは「話し言葉のイントネーションと息づかい」です。
通常、私たちの「話し言葉」を分析すると、出だしの音が高く文末は低くなる=真っ直ぐ下り坂のイントネーションで、さらに、意味のかたまりはひと息で、話しています。
例えば「ご飯を食べる」は、真っ直ぐ下り坂のイントネーションで、途中で息継ぎや「間」は取らないのが通常です。
ところが「発表する」とか「人前で話す」となると、これが途端に出来なくなることが多いんですね。
「ご飯を ⤴ 食べる」などと言った風に、助詞の「を」がグイッと上がって、言葉が小間切れてしまったり、波打ってしまったりと、途端に不自然になるので、伝わりづらくなります。※ご飯を強調したいなどの、理由がある場合は「別」ですが…
ということで、伝わるための話し方において「抑揚のコツ」は、「話し言葉のイントネーションと息づかい」を意識するということが「基本のキ」となります。
基本をわかった上で、次のステップでは「声の可能性」を広げるために、「声」をいくつかの要素に分解して効果的に相手に届ける方法をお伝えします・・・が、こちらは実践した方が、掴んでもらえると思うので、当日、じっくり、やりましょう!
・・・・・・・・・・・
「意外ですね」と仰る方も多いのですが、「話し方」を鍛えるにはまず「聴き方」を鍛える必要があります。
「聴き分ける耳」を養うということです。
「伝わるなぁ」と思う話者がいたら、なぜ「伝わってくるのか」を、「伝わってこないなぁ」と思う話者がいたら、なぜ「伝わってこないのか」を、耳をフルに使って分析してみる。
聴き分けられれば、話し分けることも出来るようになります。
9月の講座まで、どうぞ「耳」を存分に使って、聴き分けの練習をしてみてください。90分の「発表篇」の学びが、より深く実践的になるんじゃないかな、と思います。
・・・・・・・・・・・・・・・
アナウンサーになって2年目に「お前さんが出ると、チャンネルが変わる音がする」と、ベテランキャスターに言われた日から、私の中にずっと「どうしたら伝わるか?」という「問い」が住んでいます。コミュニケーションに関しては、手あたり次第、本を読み漁ったり、学びあさったりしてきました。さらには「伝わるなぁ」と思う言葉を持つ人を(ジャンル問わず)徹底的に追いかけて、真似をするということを自分に課しています。
学ぶは真似から。
最近では研修やワークショップで、ついつい「福山雅治調」になっている自分に、時に気づいて、苦笑いすることもあります。「この人のことばを、この人のおしゃべりを真似したい」と言う人がいたら、徹底的に研究するのも、ひとつの学び方です。
参考になれば(笑)幸いです。では、当日を楽しみに!
講座は、常葉大学基礎教育センター主催です。Instagramはこちら。



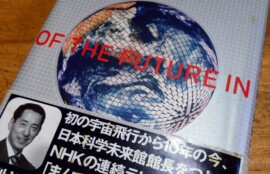



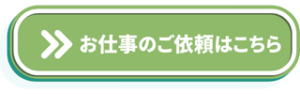









この記事へのコメントはありません。