4年前からご縁があって年に2回、有志の学生さんたちと学び合うチャンスを頂いています。常葉大学静岡基礎教育センター主催の「コミュニケーション講座」。
何と言っても、学生さんたちの真摯な学ぶ姿勢に、私自身がいつも鍛えて頂いています。事前に参加者からの数多くの「質問」が届くのも、そんな学ぶ意欲の表れでもあり、真っ直ぐな「問い」によって様々な気づきや過去の経験を呼び起こしてもらっています。
今年2回目は9月24日(水)開催の「発表篇」。既に10名の参加表明とともに(5限なのに!!!!)質問が届いています。
じゃ、ひとつめの質問、言ってみよう!!!!
Q1:人より多く言葉に詰まってしまう自覚があります。良い方法があれば教えて頂きたいです。
最近「言語化ブーム」と言われているそうで、この質問に対するアンサーは「言語化のコツ」とも言えるかもしれません。
まず「ことば」って『自分の中にどれだけ蓄えがあるか?』というのが、ひとつのポイントかと思います。本を読んだり、対話したり、日々の出来事を書き留めたり、日常の中で、どれだけ「ことば」を自分に蓄えられるか。蓄えがないと、どんなに出したくても、出せるものがない!ですよね。
そして、もうひとつ。
たとえ心の中に沢山の「ことば」が貯まっていても、「蛇口」の性能が、ある程度よくないと、うまくありません。私はこれを「ことばの反射神経」と名付けているのですが、これも、トレーニングを重ねるしか手はないと、私は考えています。
コミュニケーションは「キャッチボール」に例えられることも多いですが、トレーニングも、最初はゆっくり、まっすぐの球から始めて徐々に積み上げていく。そのうち、変化球や速球にも対応できるようになっていきます。
蓄えること、自在に繰り出せること、ともに、トレーニングです。
出来ることから、始めていけるといいですね。
具体的な練習として一番効果的だと思っているのは「書くこと」です。SNSでもメモでも日記の端っこでもいいので、今日の出来事で心が動いたことを1つ、簡潔に要約して書く、なんてのはどうでしょう?短くてOK。ネタを集める感じで、コツコツ溜めていくとよいかと思います。読書日記でも、映画日記でも、サークル日記でも、自分の関心に寄せると楽しいかな?と思います。書く際のコツは『一文は短く!取り出しやすくすること』をおススメします。
書き溜めていくと、これが「人生のネタ帳」になっていきます。一度文字にしておくと「ことば」にしやすいですよね。「最近、おススメの本で言うと・・・」「映画〇〇見た?」などなど、自分のネタ帳から、話題を取り出す練習も並行してしていきましょう。
質問してくださった方のお悩みが「入口」の課題なのか、「出口」のそれなのかはわかりません。
でもね。言葉が「詰まってしまう」ことに悩ましさを感じているということは、話したい!伝えたい!という「強い思い」があるからですよね。私は何より、その気持ちが素晴らしいと思いますし、その衝動こそが、コミュニケーション力を引き上げてくれるはずだと思います。
沢山、練習を積んで、思いのたけを伝えられるようになることを願っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
朝の生放送番組を担当していた際、放送中に東京のメーンキャスターに「けいこちゃんは、花にたとえると何の花?」と聞かれたことがありました。咄嗟に、なんといっていいのかわからず、その数日前に、友人が「私、パンジーって花が嫌いなのよね」と言っていたことが瞬間、頭をよぎり「パンジーです」と答えたことがあります。
むろん私は「パンジー」が好きでも嫌いでもなく、ただ、咄嗟に口に出たってだけで、質問してきたメーンキャスターも「きょとん」として「あ、そうなの」で会話は続きませんでした。
今ならわかります。「ひまわり」とか「朝顔」とか、自分のキャラクターに相応しいものや、朝の番組らしい名前を、きっと求めてたんだろうなぁ・・・って。
蓄えも足りなければ、機転もきかなかった20代の苦い経験です。
人は失敗して、学んでいくものです。講座では沢山の失敗から得た学びを、余すことなく(笑)、お伝えします。
学び合えるのを、楽しみにしています。
常葉大学のInstagramでも紹介いただいています。




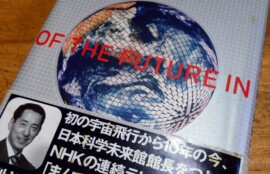

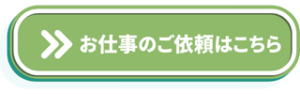









この記事へのコメントはありません。