いよいよ来週(9/24)に迫った、地元・常葉大学草薙キャンパスでのコミュニケーション講座。今年度2回目は「発表編」ということで、学内でのプレゼンや就活面談など、人前で話す機会に役立つことをお伝え出来たらと準備しています。
5限で、しかも単位取得には全く関係ない講義にもかかわらず、19人の学生さんが申し込んでくれているそうで、事前の質問も毎回、様々な角度から届いています。当日お答えする前に、自分の頭を整理するために、私も「事前」回答しています。さあ、今回もいってみましょう。
Q:理解してもらいやすくするための方法、
コミュニケーションはとにもかくにも『相手が主役!』なので、「誰に向けて伝えるのか」と「伝えた相手に、どうしてほしいのか(どんな行動を起こしてほしいのか)」を、徹底的に考えるようにしています。
相手の頭の中に入り込んで、どんな内容で、どんな言葉であれば受け入れられるかを探っていくような感覚です。探るポイントとしては、まず、相手の読解力(リテラシー)ですね。私の場合は、小学生からシニアまで、幅広い皆様にお伝えする機会があるのですが、当然!小学生と大人では、知っている言葉の数も種類も異なります。そこがずれないようにするのは基本の確認です。
次には、相手の目的・興味関心などを確認します。主体的に参加しているか、無理やり受けさせられているかなどでも、変わってきます。興味があって参加している方は、出来るだけ早く「本題」に行きたいでしょうし、そうでない方にとっては「温める時間」が必要になります。ここは事前に予測しておいて、構成も考えておきます。
前にも書きましたが、慣れないうちは、基本の型を使うことをお勧めします。「PREP」や「起承転結」です。セオリー通りに組み立てて、相手の状況に合わせて、配分を変えていくと良いでしょう。先の例のように、あらかじめ興味を持った方々であれば、頭は軽めでOKですし、興味ないのに参加している方が多い場合は、「つかみ」が肝心です。自己紹介なのか、目的についてなのか、相手の興味を惹きつける工夫ですね。「今日は、オモシロい話が聴けそうだぞ」とか「関係ないと思っていたけど、日常生活でヒントになりそうだな」など、振り向いてもらえたら、その後の展開もスムーズですね。
コミュニケーションは、キャッチボールに例えられることが多いですが、とにかく相手が取りやすい球を、最初は投げます。最初から変化球や剛速球、ましてや「消える魔球」なんてのは、どんなに素晴らしい球でも、余程のことがなければ避けた方がいいでしょう。
最初は気持ちよく、ボールをやりとりしつつ、そのうち、出来れば様子を見ながらちょっとずつ高度なやりとりにしていく感じです。
私の場合は、徹底して準備することを心がけてはいますが、いざ本番!では、準備にしばられないように、全てを捨てます。そして、目の前の人たち(伝える先の方々)に集中します。興味がありそうか、退屈してそうか、真剣に考えをめぐらせているようか・・・見ていれば大抵はわかります。その状況に応じて、必要な「球=話題」を、必要なタイミングで投げられたらいいなぁと思っていますが、事前の想像も、当日の采配も、100点満点なんてことは全くなくて💦💦、いつも反省ばかり。反省しながら、場数を踏んで、経験知を増やしてきた感じです。こんな答えだと、逆に困ってしまいますか?でも、正直、まだまだ反省ばかりです。わかっているのはコミュニケーションってのは、そうして磨いていくしかないんだろうなぁ、ということくらいでしょうか。
ついつい「内省モード」に入ってしまいましたが…経験が少ない方は、最初は前述の通り「型」を使うとよいと思います。最初から「型破り」にはなれませんから。「型」を覚えて、安定したら、そこから崩していく中で、失敗を繰り返しつつ、構成や話す順番も、いつしか的確に練れていくんじゃないでしょうか。
まず、やってみましょう!講座では、まさに「型」をお伝えした上で、お一人ずつに「1分スピ―チ」に挑戦してもらいます。私も全力でフィードバックしますね。楽しみにしていて下さい。



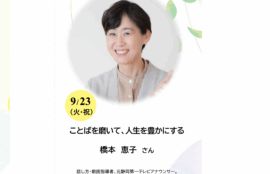
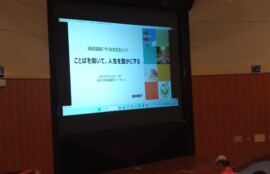


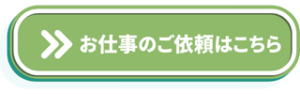









この記事へのコメントはありません。